|
|
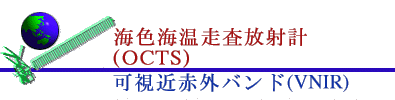
植物プランクトン色素分布画像
(左:精画像 右:粗画像) 1996年(平成8年)9月3日受信 日本
平成8年9月13日
宇宙航空研究開発機構平成8年9月3日、宇宙航空研究開発機構地球観測センター(埼玉県比企郡鳩山町)におい て、地球観測衛星「みどり」(ADEOS)に搭載された海色海温走査放射計(OCTS :Ocean Color and Temperature Scanner)の可視近赤外バンドによる初画像の取得が行われま した。
発表の画像は、日本時間の3日午前10時44分頃に「みどり」が東日本太平洋岸上空約8 00kmを通過した際に取得されたものです。
精画像は、植物プランクトンに含まれるクロロフィル−aの濃度分布を示すもので、 画像の表示範囲は1,000km x 1,100kmで、地上分解能は約700mです。
粗画像(既に科学技術記者クラブにおいて発表済み)は、植物プランクトン色素の濃 度分布を示すもので、画像の表示範囲は1,500km x 1,200kmで、地上分解能は約6kmです。
今回の画像取得はOCTSの機能確認試験の一環として実施されたものです。今後OCTSに ついては、赤外バンドによる海面温度分布観測並びに、機器の校正作業等、地上系を含 めた総合的な確認試験を予定しています。
精画像は、OCTSの可視近赤外の観測バンドで日本列島とその周辺海域を観測し、大気 の情報を除去して海中のクロロフィル-aの濃度分布を求めたものです。
赤色で表示した箇所が最も濃度が高く、カラー・バーに従って青色方向に濃度が低く なります。黒色は雲と陸地を示しております。
粗画像は、OCTSの可視近赤外8バンドから選定された3バンドのデータを1/10に衛星 上で間引き、船舶に搭載が可能な簡易な受信装置で受信し、パソコンにより処理して求 めた植物プランクトン色素(クロロフィル−aとフェオフィチン色素の両方を含む)の 濃度分布です。
緑色で表示した箇所が最も濃度が高く、カラー・バーに従って紫色方向に濃度が低く なります。白色は雲を示しております。こうした処理により、OCTSデータが漁業分野で 有効に活用されることが期待されます。
これらのデータは、以下に示す同様な傾向を表わしています。OCTSは、このような映像を3日間で全球にわたって取得することができ、海洋中の植 物プランクトン濃度分布を求めることで地球温暖化に影響する炭酸ガスの海洋への吸収 等海洋の生物科学的現象の研究に利用されるほか、水温もあわせて観測できることから 漁況予想や気象予測などに利用されます。
- 銚子〜仙台沖(常盤海域)では、緑色を示しており植物プランクトン(クロロフィ ル−a)が多いと考えられます。
- 本州南方海域は、青色から紫色を示しており、植物プランクトンが比較的少ないと 考えられます。しかし、瀬戸内海や沿岸域には植物プランクトンが多く分布している様 子が見えます。
- 粗画像に比べ精画像では熊野灘付近に渦の様なものが発生しているのが分かります。 なおこれらのデータは、今後水産庁等と共同で船舶による実測データと比較評価し、画 像処理手法の最適化を行う予定です。
問い合わせ先:
宇宙航空研究開発機構
総務部 広報室
Tel:03-5470-4127~9
地球観測データ解析研究センター
Tel:03-3224-7040
|
|
|
最終更新日:1996年9月13日 |
お問合せはこちらへ:
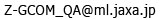
|